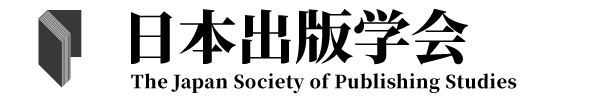■日本出版学会 第8回 MIE研究部会 開催報告
「履修生の声から考えるMIEの『わかりやすい指導』
――学生たちは何に苦心して、何を学んだか」
第8回のMIE(雑誌利活用教育)研究部会で「大学での雑誌制作教育」の実例として、目白大学と跡見学園女子大学の学生が成果発表を行った。両大学ともに2023年度にゼミや授業で雑誌を制作した学生が登壇した。
目白大学はメディア文化を学ぶ溝尻ゼミで自動販売機をテーマにした雑誌『ジハンキイズム』を制作した学生2名(白石彩絵さん、篠原麗さん)が発表した。同誌は「文学フリマ東京」で頒布、200部完売の目標を達成した。また、SNSでの広報活動でも、新規フォロワーの獲得目標(Instagram:200人以上/X:100人以上)を達成することができた。さらに、MIEの枠を超え、同大学のキャラクター「メジゾー」をデザインに使用した自販機を学内に設置するプロジェクトに発展させ、飲料企業、学生課、管理課、入試広報部に働きかけ、学生アンケートで決定した商品ラインナップの自販機設置を実現した。
雑誌編集に携わったのは、ゼミの学生10名。取材、原稿作成、デザイン、校正は学生が行い、印刷・製本は印刷所に依頼するスタイルで制作した。5~6月に企画会議、7月から取材・撮影、編集作業、広報を行い、11月に「文学フリマ東京」で頒布した。
アイディア出しからテーマ決定のプロセスでは、各人が企画書を作成し、それぞれの要素を入れ込みながら全員が納得する形で企画を詰めていった。夏休みが取材の佳境となるので、進捗を可視化するツールを作成して全員で共有。取材準備や取材後のお礼などルールを定め、LINEも駆使して認識のずれや共有漏れがないように工夫した。教員は、学生の主体性を重んじ、内容よりも技術的な助言(原稿の添削、印刷所への入稿に関する指導、写真の明るさや見出しの配置など)を行った。
雑誌制作を経て得られたことは「一から企画を考え形にし、それを人に届けた達成感」「ターゲットに合わせた雑誌制作とSNS運用の難しさ」「実際に手に取ってくれた方からの反響や取材先の企業とのつながり」だったと報告をまとめた。
跡見学園女子大学は、富川淳子先生による「ライティング特殊演習(編集)」の授業で雑誌『Visions』13号を編集した学生4名(徳永里奈さん、中村悠海さん、米村莉乃さん、橋本優衣さん)が発表した。『Visions』は同大学の文学部現代文化表現学科の学科報と位置付けられており、学科の学びを活かして目指したい職業を特集している。2023年度は、この授業の履修生24人が富川淳子先生のご指導の下で制作、eスポーツ国際大会を開催した人々の仕事をテーマとした。テーマ設定は教員が行う。学生一人が必ず責任をもって一人を取材することを授業のポリシーとしている。
本紙の特色はデザイナーやカメラマン、校正者など、プロと協働して編集を行うことである。出版社の編集者と同じプロセスで雑誌制作を体験する。登壇した学生たちは、プロとのコミュニケーションに苦心し、同時にそれが大きな学びになったことを発表した。ラフレイアウトをつくってデザイナーに誌面構成の意図を伝えることの難しさ、カメラマンとの日程調整、印刷所の人にわかりやすい校正記号の使い方などが学びに直結している。この授業では、教員だけでなく外部のプロフェッショナル達も指導者になっていることが分かった。
教員は実務の現場でいうならば編集長であり、学生たちは編集部のスタッフとして編集を行う。発表中、「上司である先生」、「プロと仕事をする」といった言葉もあり、この授業がキャリア教育として機能していることが伺えた。実際に登壇者のうち1名の学生が『Visions』を印刷している会社に就職を決めた。
発表後の質疑応答では、「取材先となる企業とのつながりは教員がつくったのか」「台割はどのように決めたのか」「プロジェクト開始前の参加者の読書経験」「SNSの運用上の工夫や目標設定」「業務の担当・チーム分けの方法」など多くの質問があった。予定していたディスカッションの時間が取れなくなるほどの質問が出されたのは、MIEの実施方法が大学によって違い、教員がその最適解をまだ模索しているからだと思われる。今後、さらにMIE実践のケースを集め、教育上の工夫を研究していきたい。
日 時: 2025年2月6日(木)18:00~19:30
開催方法: 会場での対面形式とZoomによるオンラインの同時開催
会 場: 跡見学園女子大学 文京キャンパス 2302教室(2号館3階)
参加者: 31名(会員21名、非会員10名。うち、オンライン参加者12名)
(文責:元永純代(跡見学園女子大学文学部現代文化表現学科 准教授))